突然の客人の来訪にスザクはただ目を丸くしていた。
ルルーシュはたまに訪れてくれていたし、シュナイゼルはまた来ると言っていたからいいとして、問題はジノだ。
今まで顔を見せなかったくせに、いきなり何だと言うのだろう、という疑問が浮かぶ。
「いやいや、すまないね。具合が悪いのに」
気付けば2人ほど付いて来てしまったよ、と喰えない態度で笑うシュナイゼルに、後ろでルルーシュが不満げに眉を寄せた。
「それで、あの…用件は…?」
思わず問いかけると、用件が無ければ来てはいけないのかい?と返される。
本当に喰えない人だ。
思わずこめかみに手を添えて溜息をつく。
この人は、忙しいのではないのか、一応宰相閣下なのに。
「シュナイゼル殿下…」
「またよそよそしい名前で呼ぶね。悲しいな」
「………シュナ様。もしかして、ただ雑談しに来た、と?」
まさか、と思い問いかけると、シュナイゼルは満足げにこっくりと頷いた。
もしかして。
「後ろの2人も?」
視線を移すと、ルルーシュは視線を僅かに泳がせ、ジノにいたっては思いっきり顔を反らした。
それを見て、はぁあああ、とまた溜息を零す。
「スザク、そんなに大きな溜息をつくと幸せが2つも3つも飛んでしまいそうだよ」
誰が溜息をつかせているというのだろう。
「…シュナ様。冗談はともかく、何か御用があったのでしょう?」
このままではどこまでもはぐらかされそうだ、と思い切ってこちらから話題を振ると、シュナイゼルの瞳が僅かに揺れる。
シュナイゼルはいつもそうだった。
幼い頃から、スザクに会いに来るときは何か用事があった。
それは、日本のことを探るためだったり、ストレス発散だったり、プレゼントを渡しに来たり様々だったけれど。
ただ顔を見に来る、という無駄な行為は滅多に行わない人だった。
案の定、シュナイゼルはお見通しか、と肩を竦めると後ろの2人を振り返る。
「…この2人がスザクに聞きたいことがあるらしくてね。スザクが答えて良いと思うなら答えてあげてくれないかな?」
いきなり話を振られた2人は一瞬驚いたように目を見張ったが、ジノがすっと一歩前に出た。
「私がこれからする質問はスザクにとって辛いものだと思う。だから、答えられる範囲で教えてくれないか?」
「…わかった」
「私と出会う前、終戦直前…私の知らないスザクを教えて欲しい」
ジノの質問を聞くと、スザクはひゅ、と息を呑んだ。
とうとうこの日が来た、と瞳を揺らがせる。
決して言うまいと、特にルルーシュだけには知られるまいと思っていた真実。
けれど、いつかは話すべき時が来るだろうと心のどこかで思っていたもの。
「スザク。話しにくいことだということは分かっている。けど、俺は俺に起きた全てを知りたい」
ルルーシュは真っ直ぐと揺らぎ無い瞳で見つめてくる。
どこまでも真っ直ぐで、芯をしっかりもっていて、頑固で強情な君。
そんな君に言えと言われると断れないことくらい分かっていた。
「…私が知っていることは、全部話すよ。生まれてから今までの生い立ち」
私は枢木神社の巫女として生まれた。
神様にお仕えするのが仕事で、いつかは父さんのためにどこかのお偉いさんと結婚するのだと教え込まれて育った。
それを当然だと思っていたし、それが私の幸せだと信じて疑わなかった。
ただ、母さんだけが、そんな私を哀しそうな目で見ていた。
母さんは出来なかったから、スザクには恋愛結婚してほしいとそう言って。
レンアイケッコン、というものがどういうものか当時の私には分からなかったけれど、とても素晴らしい物に見えた。
だから、心のどこかで、恋愛結婚というものに夢を抱いていた。
やがて成長していくにつれて、周りの女の子はレンアイに夢中になっていった。
初恋した、とか。誰かに告白したとか。
そんなことから程遠いと思っていた私はレンアイしたいと感じるようになっていった。
母さんが言う、レンアイケッコンをしたいと。
しかし、そんな甘いことを言っていられないほどに世界情勢は酷くなっていく。
元々良いとは言い難かったブリタニアの関係が日に日に悪いものへとなっていったのだ。
戦争まで始まって、人々の心は反ブリタニアへと染まっていった。
そんな折、ブリタニアから2人の子供が人身御供として家にやってきた。
ブリタニアは敵。
そう教えられていた私は、彼らの世話をスザクに押し付けた父を恨んだ。
どうして私が…そう思うものの、昔から社交界へと連れまわされていた私は仮面を被ることは得意だった。
「お世話を任されました、スザクです。何かあれば、遠慮なくお申し付け下さい」
「じゃあ、お友達になってくれますか?」
部屋へ案内し、一仕事終えたと思った私に言われたブリタニアの少女からのお願いは、何とも意外なものだった。
彼女は私を敵だと思っていないのだろうか。
彼女の兄は、ギラギラとした瞳を私に向けているのに。
「…お友達、ですか?」
「はい。私もお兄様も年の近いお友達がいなくて。あ、私はナナリーです」
遠慮がちに差し伸べられた手をそっと握ると、ナナリーはとても嬉しそうに笑った。
それから、毎日はどんどん変わって行った。
ナナリーを中心にして。
ルルーシュは最初こそ警戒していたけど、ナナリーには敵わないらしく、すぐに警戒を解いた。
彼は賢くて、スザクやナナリーに色々なことを教えてくれた。
私はお返しというわけではないけれど、人目を盗んではリンゴや桃等を彼らの住む土蔵へと運んだ。
時折、冷たいスイカを1人では食べられないほど用意していてくれたり、母さんは気付いていたようだけど。
ナナリーを背負って野山へ遊びに行ったりもした。
ルルーシュは皇子様だからなのか、女の私よりも体力が無くて。
華奢で軽いナナリーを背負って歩くのはいつも私の役目だった。ルルーシュは不満そうだったけど。
私達が親友になるのは、あっという間だった。
そんなある日のことだった。
ルルーシュと私、2人呼び出された席で、婚約のことを父さんから告げられた。
レンアイケッコンに憧れを少しでも抱いていた私は、正直嫌だった。
ルルーシュは嫌いではないけれど、好きだけど、恋ではなかったから。
土蔵への帰り道、彼の「今だけだよ。僕達が大人になる頃には解消されるさ」という言葉が嬉しかった。
婚約の話が出たときにルルーシュの頬が赤く染まったのを知らないフリをして。
「そうだ、今日は泊まっていくんだろう?」
「うん。ナナリーと約束していたし」
頷くと、ルルーシュは嬉しそうに笑って。
彼の笑顔は好きだった。ナナリーの笑顔と同じくらい。
2人のためなら、何でも出来ると思うくらい好きだった。
ずっと、親友でいたかった。
「ねぇ、お兄様。私とスザクさんとお兄様。3人ずっといれるといいですね」
夜も更けてうとうととし始めた頃、ナナリーが小さな声でルルーシュに話しかけた。
私は起きていたけれど、彼女達に背を向けて、狸寝入りをして、じっと話に耳を傾けて。
「大丈夫だよ。今日、スザクと婚約したんだ。だから大人になってもずっと一緒だ」
ルルーシュの言葉は、昼間とは正反対で。
ナナリーを思っての言葉だったのかもしれないけれど、ツキリ、と胸が痛んだ。
嘘つき。大人になる頃には解消だって言ったくせに。
ルルーシュの本音はどちらなのだろう。
ぐるぐると頭の中で、思考がハツカネズミのように回って、私はその夜、眠れなかった。
夏の暑さは日に日に増していき、ひぐらしの声はどんどん音量を増していく。
私は藤堂先生との稽古のあと、ふと父さんの部屋の前を通りかかった。
「ナナリーを始末すればいいんですな?」
聞き捨てなら無い言葉だった。
そっと襖を開けると、壁に向かって何やら電話をしている父さんの姿があって。
「えぇ、順調だよ。先程ナナリーを土蔵から連れ出して裏山の小屋へと移したと報告が入った」
ねぇ、父さん。始末って何?ナナリーをルルーシュから引き離して、どうするつもり?
「目も足も不自由な子供など、殺すのは簡単ですよ。何、心配しないで下さい」
くくくっ、と喉で笑う父さんは今まで見たこともない、顔で。
まるで、昔話に出てくる鬼のようだった。
ガタガタと足が震える。
けれど、ぼうっとしている時間は無かった。
早くしないとナナリーが殺されてしまう。
私は忍び足でその場から逃げると、全力で裏山を駆け上がった。
父さんが言う裏山の小屋は知っていたから、そこへ向かって一目散で。
しばらく走っていると目の前に男に抱きかかえられているナナリーを見つけて。
稽古で使っていた木刀を思い切り振りかぶって男に叩きつけた。
相手は不自由な少女1人と侮っていたのだろう。
2人しかいなくて、そのままもう1人の鳩尾に木刀を叩きつけると、簡単に男達は倒れ伏した。
「ナナリー、行くよ」
ナナリーをおぶって裏山の草むらへと身を隠す。
草木の良く茂った裏山は子供2人くらい簡単に隠してくれる。
土蔵へ戻ったからといってナナリーの身の安全は保障されない。
私は、3人で作った子供がやっと入れる秘密基地へとナナリーを隠すと、大急ぎで家へと戻った。
とりあえずルルーシュにもこのことを伝えなければ。
けれど、土蔵は空っぽで。
ナナリーを探しに出て行ってしまったのか、それとも捕まってしまったのか。
どちらにしろ、私が次に取れる行動は決まっていた。
台所からこっそり包丁を持ち出して後ろ手に隠す。
父さんを止めなければ、その一心で父さんの部屋の襖を開いた。
正装をした父さんは酷く苛立たしげで。
理由はきっとナナリーを私が助けてしまったからなのだけれど。
入室するなり、話を早くしろ、お前に割く時間は無いと怒鳴りつけられた。
「父さん、戦争を止めて下さい。ルルーシュ達を助けたいんです」
言葉を発したとたん、カッと父さんの顔は真っ赤に染まって、あの鬼のような顔をした。
「お前まであのブリキに感化されたか!馬鹿者め!!」
何を言い募っても駄目だった。
父さんは全く受け入れてくれなくて、とうとう私に背を向けてしまった。
話も聞いてくれないのか。私はただの道具なのか。私はただ、あの人達を助けたいだけなのに。
気付けば、私の両手は真っ赤で、父さんの背中には深々と包丁が刺さっていた。
涙どころか、悲鳴すら出なくて、足がガクガクと震えて、その場に座り込んだ。
父さんの倒れる音を聞いたのだろう、駆けつけた藤堂によって、私は父さんと離された。
桐原に、は、ここから立ち去れと、と言い渡され。
私は血で濡れた体を洗い落とされると、真っ白なシャツを着せて追い出された。
罪を償うことも許されなかった。ただ、家を追い出されただけ。
「…そうだ、ナナリー…」
ナナリーを迎えに行くと、彼女は何も知らない笑顔で迎えてくれた。
持ってきた車椅子に彼女を乗せて、ルルーシュを何日か探してみたけれど、見つからなくて。
とりあえずナナリーだけでも安全なところへ、とブリタニアの軍のある場所へ向かって歩いて。
「それで私が拾った、というところだね」
「はい、そうです」
こくん、と頷くスザクの生い立ちにジノは息を呑んだ。
断片的に聞いていたし、辛かったことも聞いていたけれど、それでもたかが10歳の子供に起こったことにしては重く。
初めて聞いたであろうルルーシュは眉間に皺を寄せて、拳を握り締めていた。
「スザク…ありがとう、話してくれて」
ルルーシュは搾り出すようにそれだけ言うとぎゅう、とスザクを抱きしめた。
その背を、子供をあやすようにぽんぽん、とスザクの白い手が撫でる。
「あと…ありがとう。ナナリーと俺を守ってくれたんだな」
ルルーシュの言葉にスザクはまん丸な目を更に大きく見開くと、顔をぐしゃぐしゃにして泣き始めた。
子供のようにわんわんと。
ずっと、心のどこかで求めていたのだろう。
ありがとう、という言葉を。
ルルーシュは、スザクは本当に泣き虫だな、なんて苦笑を浮かべながらずっと背中を撫でていた。
そっと手を伸ばしてスザクの髪をジノが撫でると、ルルーシュの肩に埋めていた顔を上げて。
スザクは涙でぼろぼろになりながらも精一杯笑った。
その顔はお世辞でも綺麗なんて言えない顔なのに、今まで見た笑顔の中で一番可愛らしかった。
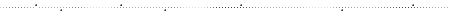
あと2回くらいで終わらせたいなぁ。次の連載も始めたいし。
案の定ジノスザ♀ですが(女体好き過ぎだろう)
あと少しお付き合い下さいませー。
to be continu...